前回、芝居に救われた命では、居場所がなくなり死ぬことも考えた私が、芝居と出会って救われたという話を書きました。
進学校だったので、部活にかまけていると成績に影響してくるのですが、もうその頃の私はそういったことには動じないくらいに芝居にのめり込んでいたのです。
将来は芝居を仕事にしたい、芝居をずっとやっていたい、そう考えるほど奥の深いものであると感じたし、自分の中で救われたという思いが強かったんだと思います。
ですが、進路を決める段になって問題が起きます。
芝居の道に進みたいという私に対して、母が異論を唱えたのです。
猛反対というのでしょうか。とにかく芝居なんかで食べていけるわけがないと頭ごなしに言われる始末。私の芝居を観たこともないのに、そんなことできるわけない、あなたの実力が伴っているわけがないと言います。
私は憤慨しました。どうして観たこともないのにそんなことがわかるんだと反発しました。すると母は、観なくても自分の子どものことはわかるという言いようです。まったく、冗談じゃない。
親に反抗したことはなかった私が、その時ばかりは1週間くらい母と口をきかなかったのを覚えています。
本当にひどいと思いました。
娘の話を考える余地もなく否定する母の前で、私は自分がまるごと親に否定されたような気になったのです。
今思うと、本当にやりたかったらそこで押し切ることができたはずです。ただ、親の庇護のもとにある高校時代ですし、大学進学にあたっては多額の費用がかかるわけですから、進学させてもらう立場である自分に選択の余地はないと思ってしまったんですね。
私は1週間の母との絶縁状態の間に、諦めの感情に支配されるようになります。
そんな頃、演劇部とは別に立ち上げた劇団を主宰する友人から、ある告白を受けることになります。
月が赤くて、大きな宵でした。話があると呼び出され、月の出始めた宵のうちで家の周りをぐるぐると何周もしながら話された内容は、友人が芝居をやめるという決意でした。
芝居の道には進まない、建築を志すために、建築の大学を受験する、そんな話でした。
友人の才能に心酔していた私は、ずっとその友人についていくものだと思っていたので、衝撃が大きかったですし、裏切られた思いが強く残りました。
そんな風に、私が芝居の方向に行くのを阻止する力が二つもあると感じたことから、私も徐々に芝居への情熱を失っていくことになります。
母は私に、看護師になって欲しいと考えていました。病気がちだった幼いころの私が今こうして生きているのは、医療のおかげ。だから医療に恩返しができるよう、世の中の人々のためになることを仕事にしてほしい。そういった希望を持っていました。
友人が離れて行ってしまうという淋しさに、芝居そのものにも見捨てられたような気持になり、私はそこで芝居への道を半分諦めることになります。
半分というのは、まだ完全には離れるつもりがなかったことを意味します。
親に進学資金を出してもらう立場である以上、親の意向に沿ってみよう。確かに自分は医療に命を救われたし、資格を身につけることは強みになると、母から言われたことに納得し、大学には進む。でも、その傍らで芝居を続け、看護師の資格を取ってしまった暁には、芝居を本気でやればいい、そんな風に考えたのです。
今だったら、看護師の資格という逃げ道を作っていたことが、芝居の道に進まなかった原因だし、それでは上手くいくはずがないとわかりますが、当時の私はそれが合理的な考え方で、親を満足されることもでき一石二鳥だと考えたんですね。
結局、芝居に対する私の想いはその程度だったということなのでしょう。
友人がいるから芝居をやっていたのだと思います。自分がどうしてもやりたいことではなかったということなんだと、冷静に考えてそう思います。
そんなことがきっかけで、私は「演じること」から離れていったのです。
次回、看護の道を歩き始めた頃 -人生の棚おろし⓺-」では、大学に入学して看護を学ぶようになってからの話です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました(^_^)
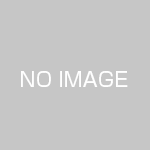






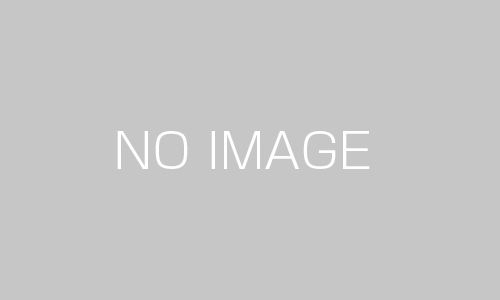


この記事へのコメントはありません。